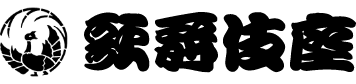四季で楽しむ江戸グルメ
江戸っ子とねぎま鍋

江戸時代マグロは下魚とみなされていて値段が安かった。マグロは現在の相模湾や伊豆、千葉などの海で獲れ、日本橋の魚市場に運ばれた。特に大漁の時は値段が安く、文化7年(1810)12月初めよりマグロが夥しくとれたときは、大きなものでも1尾1500文で売られている。1文30円として、4万5千円で買えたことになる。
滝沢馬琴も「天保三年(1832)壬辰の春二月上旬より三月に至て、最下直也。いずれも中まぐろにて、二尺五六寸或は三尺許(ばかり)のもの、小田原河岸の相場、一尾二百文也など聞えし」と記している(『兎園小説余禄』)。これだと1尾6000円位で売っていたことになる。桁違いの値段だ。
江戸っ子は買い求めたマグロを刺身でも食べていたが、ねぎま鍋も好んで食べていた。江戸時代、ねぎま鍋は「ねぎま」といい、名前どおり長ネギとマグロを煮た料理で、その早い例は、山東京伝の黄表紙『花東頼朝公御入』(寛政元年・1789)にみえる。そこに登場する人物の一人が「おいらはやつぱり、ぞくにねぎまであつかん(熱燗)がてん(点)だ」(ねぎまを肴に熱燗で一杯やるが最高)、といっている。
このころにはねぎまの名が通用していたことがわかる。ねぎまは居酒屋の人気メニューになり、居酒屋では大きな平椀に盛られていたが、鍋で提供する店も現れた。脂っこいトロは捨てていたといわれているが、食材をむだにしない江戸っ子のこと、トロはねぎまに使っていたはずだ。マグロのトロはねぎまにして食べるとうまい。
お勧めの日本酒
-
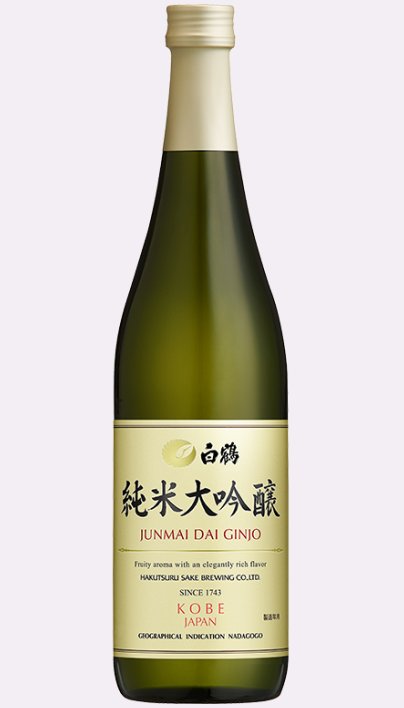 白鶴 純米大吟醸低温でじっくりと醸した純米大吟醸酒です。りんごや洋ナシのような豊かで華やかな香りと、純米ならではのふくらみのある味わいです。
白鶴 純米大吟醸低温でじっくりと醸した純米大吟醸酒です。りんごや洋ナシのような豊かで華やかな香りと、純米ならではのふくらみのある味わいです。
純米大吟醸の透明感のある味わいは、マグロの旨味を引き立てつつ、後味をすっきりとさせます。
白鶴 純米大吟醸 | 白鶴酒造株式会社 (hakutsuru.co.jp)