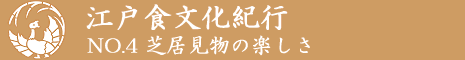江戸時代の一般の人々の娯楽は、現在のように多種多様ではありませんでしたから、芝居見物は想像以上に大きな楽しみであったようです。
江戸での芝居興行は、明け六ツ(午前6時ごろ)から、暮七ツ半(午後5時ごろ)までが原則でしたから、芝居見物に行く日は一日がかりでした。
当時の芝居の演目は、ふつう年に4、5回変わり、役者は各座ごとにきまっていて年に1度10月に入れ替わりましたので、11月は芝居の世界では顔見世の特別の月でした。
そのため芝居小屋のある芝居町では11月は正月に当たり、大変な人出で混雑しました。江戸時代の川柳集「柳樽(やなぎだる)」にも、「眼にも正月顔見世の花やかさ」とあります。
見物客には芝居茶屋を通して入る上級の客と、木戸から入る一般の客があり、上級客の見物席は棧敷で、一般客は土間が普通でした。
幕府の奧医師で蘭方医だった桂川甫周(国興)の二女今泉みね(1855 - 1937年)の、晩年の昔語りを記録した『名ごりの夢』(東洋文庫)の中には、「あのころの芝居見物」として、若いころの芝居見物の楽しさが記されています。社会的地位の高い人たちにも、芝居見物が大きな楽しみであったことや、芝居茶屋の役割もよく伝えています。当時、芝居町は浅草猿若町にあり、桂川邸は築地にあって、道を隔てて隅田川に面していました。「あのころの芝居見物」の一部をご紹介しましょう。 |
|
「お芝居といえばずいぶんたのしみなもので、その前夜などはほとんど眠られませんでした。一度は床に入ってみますけれど、いつの間にかそうっと起き出して化粧部屋にゆきます。百日蝋燭の灯もゆらゆらと、七へんも十ぺんもふいてはまたつけ、ふいてはまたつけ大へんです。やがて七つどき(午前4時ごろ)にもなりましょうか。みんなを起こしてそれからが公然のお支度になります。それ着物それ帶といったように、皆の者はあちらにゆきこちらにゆき、立ったりすわったりにぎやかなこと、にぎやかなこと。そのうち供まわりの方の支度もできまして、いよいよ屋根ぶねで浅草へ参ります。大勢の時は屋形ぶねでございます。船つき場へはちゃんときまった茶屋から出迎えがありますが、手に手に屋号の紋入り提灯を持って「ごきげんよう、いらっしゃいませ」といかにも丁寧に、手を添えて船から上げてくれます。」
|
|
|
|
芝居町の通りの両側には、のれんをかけた茶屋が並んで軒先の提灯の灯も美しく、夢見心地で茶屋に入り、奥座敷か二階でしばらく休み、時がくると見物席まで案内されます。
芝居の幕間ごとに客は茶屋へ引きあげて、着がえをしたり時刻によっては食事をしたりします。食べ物については次のように語っています。
|
|
| 「またさじきの中におすもじ(お寿司)やお菓子や水菓子(果物)などが運ばれてみんなで賑やかにいただきましたが、上気して喉がかわいた時の水菓子のおいしさは今もおぼえています」 |
|
|
注釈)
桂川甫周(国興)は「かつらがわほしゅう(くにおき)」と読みます。 |