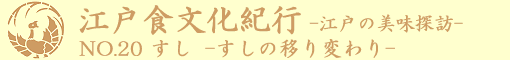|
| 現在、すしといえば握りずしを連想しますが、すしの歴史は古く、馴れずし、生なれ(なまなれ)、押しずしなどを経て、握りずしが作られるようになったのは、江戸後期の文政年間(1818-30)といわれています。 |
|
| すしの始まりは魚の貯蔵法で、塩漬けした魚を半年以上の長期間米飯に漬けておくと、米飯の乳酸発酵で酸ができて腐敗菌の繁殖をおさえ、魚肉は酸っぱくなります。また魚肉自体も自己消化でたん白質が分解して、旨味のあるアミノ酸などができておいしくなります。これを馴れずしと呼び、粥状になった米飯は捨てて魚肉だけを食べるものでした。 |
| |
| 奈良、平安時代のすしは馴れずしでしたが、室町時代になると、馴れずしよりも漬ける期間が1ヶ月前後と短い生なれが作られ、飯も魚肉とともに食べるようになりました。江戸時代も初期のすしは馴れずし、または生なれでした。「義経千本桜」の3段目に登場する鮎ずしも生なれのすしです。 |
|
江戸中期の延宝年間(1673-80)になると、乳酸発酵による酸味ではなく、飯に酢を加えてつくるすし飯が考案されて押しずしがつくられるようになりました。
押しずしは箱ずしとも呼び、すし飯を四角のすし枠に詰め、その上に薄切りの魚介類などのすし種をのせて蓋をし、重しをかけて押してから枠から抜き、切ったものです。 |
|
| 上の図の屋台店のすしは、『江戸爵』の刊年からみて押しずしで、図の右端にはすし枠を担ぐ人も見えます。 |
|
|
|
|