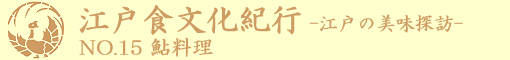初夏の若鮎、秋の落ち鮎など、鮎は季節感の濃い魚です。また鮎は味が淡白で、姿が美しいことから日本人の好みに合い、古代から高級魚とされています。
江戸時代にも多様な鮎料理があって、『料理物語』(1643)には「なます 汁 さしみ すし やきて かまぼこ」などがあげられています。料理法は鮎の成育時期によるので、次に鮎の一生をまとめてみました。
|
| |
| 鮎の卵は秋に川の中・下流の川底の石に生み付けられ、孵化(ふか)した稚魚は流されて海へ入り、冬の間は海で過ごします。春には5、6センチに成長して川をさかのぼり、上流の川底の石についた石あかとよぶ藍藻(らんそう)や珪藻(けいそう)を食べて育ち若鮎になります。石あかを食べた鮎の肉は香気があるので香魚(あゆ)とも書きます。夏の間上流で過ごした鮎は、秋になると産卵のため中・下流へ下りますが、これを落ち鮎とよびます。産卵を終えた鮎の大部分は寿命がつき、1年で一生を終えるので年魚(あゆ)とも書きます。 |
|
| 夏の鮎は塩焼にし、蓼酢(たでず)を添えるのが一般的ですが、古代から江戸時代には鮎鮓もよくつくられています。「義経千本桜」の三段目の鮓屋には鮎鮓が登場しますが、この鮓は生馴れ(なまなれ)で、塩漬にした鮎を米飯と交互に鮓桶に詰め、数日から1ヶ月ほど漬けて、乳酸発酵の酸味が少し出たところで食べるものです。古代の鮎鮓は馴れずしで、数ヶ月から2年も漬け、魚だけを食べるものです。 |
|
| 落ち鮎は干すか焼くかしてから煮た煮浸し、また粕漬にもしています。鮎の内臓の塩漬は「うるか」とよび、用いる部分によって、子うるか、白うるかなどがあります。 |
|
|
|
|