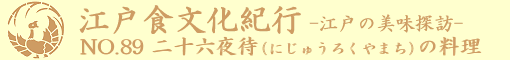|
| 江戸時代には、旧暦の1月と7月の26日の夜に、月の出るのを待って拝む行事を二十六夜待といいました。この日の夜半すぎに出る月は、出る間際の光が三つに分かれ、瞬時にまた一つになるように見え、その光の中に阿弥陀・観音・勢至(せいし)の三尊の姿が見えるといわれ、これを拝むと幸運が得られるという信仰が古くからありました。1月は寒いので、7月の二十六夜待が、江戸を中心に盛んに行われました。 |
| |
江戸では、月の出を拝むことのできる海岸や高台に人々が集まり、中でも高輪や品川の海岸は多くの人で賑わい、料理屋は繁盛し、路上には酒食の屋台が並び、歌舞音曲などの催しも行われました。
『江戸名所図会』(1834)にも「高輪海辺七月二十六夜待」としてその光景が描かれていますが、この行事は天保の改革以降は規制を受けてめっきり衰えたといいます。
|
| |
上の絵は、二十六夜待の夜の海を見はらす料理屋の光景で、酒食を楽しむ3人の女性がいます。中央の徳利の右側の深鉢は、盃を洗う盃洗ですが、左側の深鉢は水物(みずもの)のように見えます。
水物は水の物とも呼び、夏に冷水に栗・茄子・胡瓜などを食べやすい大きさに切って浮かべ、箸や指先でとって、塩などをつけて食べるものでした。
|
|
 |
|
|
右側には大皿に盛った蟹が見えます。現在は蟹といえば、ズワイガニやケガニを連想しますが、江戸時代の海産の蟹はおもにガザミ(ワタリガニ)でした。魚介類の中では下の部で、料理書にもあまりみられませんが、肉の多い雄を蒸して調味酢を付けて食べたのでしょうか。
|
|
|