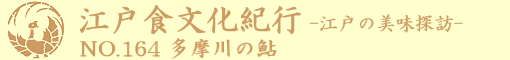|
多摩川(玉川)の源流は、山梨と埼玉の県境の笠取山にあり、下流は六郷川の名で東京湾に注いでいます。江戸時代の承応3年(1654)に、羽村から多摩川の水を江戸市中に引く玉川上水が完成し、市民の飲料水や生活用水、また農業用水にも利用されていました。
絵で見るように自然のままの多摩川の清流には鮎も多く、絵には釣竿をかついだ人や釣糸を垂れる人、四つ手網を引き上げる人など、鮎をとる人々が点在しています。秋の鮎は初夏の若鮎に対して落鮎(おちあゆ)または錆鮎と呼ばれ、『柳多留』に「玉川の秋は景色も鮎も錆」の句があります。
|
|
|
秋に川で孵化した鮎の稚魚は流れにのって海に入り、東京付近では東京湾や三浦半島の岸近くの暖かい海で冬を過ごします。桜の咲く頃には5~7センチに成長し、河口で淡水に体を慣らしてから、群をなして川をさかのぼり始めます。海にいる時の餌は動物性のプランクトンですが、川に入ると珪藻類、藍藻類などの水垢(みずあか)と呼ばれるものが餌になります。水垢を餌にして上流へ向かうのが5、6月頃で、10センチ前後の若鮎です。育ちながら上流へ向かった鮎は、産卵が近づいた9月頃には川を下り始め、多くは河口から4キロくらいの産卵場で、清流の川底の小石の上に産卵します。この産卵場まで川を下る鮎を落鮎と呼び、体が黒ずんでくるので錆鮎とも呼びます。産卵後間もなく雌は死に、雄も産卵場付近で生涯を終えるので、寿命がふつう1年のところから鮎は年魚と書きます。
|
|
|
鮎の旬(しゅん)は7月中旬から約1ヶ月といわれ、水垢だけを餌にするため腸に生じた香気と渋味が喜ばれます。江戸時代の料理書にも落鮎の料理は少ないのですが、『黒白精味集』(1746)には、子持鮎の色付炙(いろつけやき)、炙浸(敷かつお)、冷煮物(やき鮎、ひしこ、青まめ)などがあります。
|
|
|
|
|
|
|
|